 |
 |
地区内8箇所から、障がいのある皆さんを避難所の辻小学校へ案内しました。今回の訓練では、所属の介助ボランティアや家族が同行されていたこともあって、大きな混乱も無く避難は済みましたが、誘導に当たった自治会担当者から「初めてのことで、戸惑った。障がいについて改めて学びたい」との感想が話されました。 |
|
 |
 |
避難所の体育館に入る前に、避難する要件とともに建物の安全確認のための「罹災建築物応急危険度判定」の説明がありました。言わば各家庭の近くの空き地などでで避難生活をすることに理解を求めたものです。
入館後は、受付の記録紙に登記した後、それぞれ自由意志で、障がいのある人もできる範囲で会場設営に当たりました。 |
|
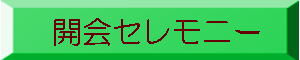 |
清水区長臨席のもとで開会セレモニーが行われました。自主防災会長(連合自治会長)、実行委員長(地区防災指導員)、清水区長、障害のある人代表、静岡市障害者協会事務局長、実行委員会事務局のあいさつには、前述の訓練の狙いへの熱い思いが込められていました。
また、参加者の最前列に整列した10台の車椅子や手話通訳の様子に、自主防災会の皆さんも災害時に必要となる支援の重さを感じ取られた様子でした。 |
 |
 |
|
 |
 |
消防署の指導でAEDの取り扱い、三角巾の取り扱いなど救急救命訓練を学びました。
心臓マッサージ、人工呼吸を覗き込む顔、三角巾に自分で取り組む姿に、「できることは・・・」とした障がいのある人たちの意気込みを感じました。
また、会場に掲出された火災報知機に、各家庭での設置の必要を感じあいました。 |
|
 |
長泉町からの友情出演もあって、多くの防災用品が展示されました。
プライバシー保護にための間仕切り用ダンボールもありましたが、この訓練で特に話題となったのが簡易トイレ。障害者用仮設トイレは無論のこと、一般用も色々設置され、災害時のため体験を勧められました。
また、ボランティアネットワークの皆さんによって「ほのぼの灯り」実演や非常食の紹介がありましたが、試食した乾パンはおいしくなく「災害時に備えて工夫が必要」との感想がありました。 |
|
|
|
|
|
写真をクリックしてください。大きく変わります。 |
 |
 |
この訓練で始めて披露された「巨大すごろく」。 10メートル四方の広さと30センチもあるさいころの大きさに驚かされました。
普通のすごろくと同じように、さいころの出た目により進んだり戻ったりするもので、所々に出る防災クイズに答えながら遊びますが、問題に結構難しいものもあって障害のある人も交えながら楽しいひと時を過ごしあいました。 |
|
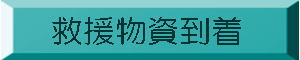 |
途中、先進地、静岡市葵区「千代田東自主防災会」(平成20年12月宿泊訓練開催)の皆さんが激励に訪れてくださいました。
救援物資として頂戴した卵とジュースは夕食のメニューに加えさせていただきましたが、寒さの中に心の温まる思いができたと、感激を味わいあいました。 感謝、感謝。 |
 |
|
 |
写真をクリックしてください。大きく変わります。
夕食メニュー
ご飯 1合
トン汁
缶詰 1缶
ゆで卵 1個 |
夕食は、車椅子の一部の方には机が用意されましたが、床に敷き詰めたダンボールの上に車座になって食べました。
ご飯はハイゼックスで炊き、トン汁は缶詰に野菜を加えたものでしたが、非常食とはいえやや量が少なかったとの感想がありました。ただ、トン汁はお変わりをした方もあったようです。
なお、ご飯は非常時を想定して、水の代わりにジュースやコーラ、コーヒーを使ってみましたが結果はいかがでいたでしょうか。 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
夕食後、映画サークルの皆さんにより「阪神淡路大震災」の記録映画が上映されました。
リアルに再現される災害の爪あとは、見る人に「私たちも備えなければ」との思いに浸らせました。 |
 |
|
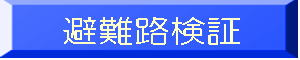 |
 |
寒さに耐えられず、就寝用毛布が配布されましたが、昼間の避難誘導時に撮影された写真をもとに災害ボランティアネットワーク代表から避難路の安全確認について説明がありました。
平素の配意の必要を学びました。 |
 |
|
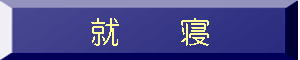 |
 |
いすにブルーシートをかけ風除けとし、寝袋に入ったり毛布にくるまれたりして眠りにつきました。
救護所として準備した暖房テントは利用されたものの、安全確保のため用意したエアコン付図書室の利用はありませんでした。
途中、2時間交代で見回りましたが特筆された異常はありません。 |
|
 |
この宿泊訓練では、時期的に極寒が体験できるものと思っていましたが、当夜の最低気温は朝6時の6.2℃と意外な結果になりました。
障がいのある人の一部に体調不良を訴える方がありましたが、6時に起床、みんなで毛布やブルーシートを片付け、6時30分からラジオ体操で体をほぐしました。
|
 |
|
 |
朝食メニュー
ご飯 1合
けんちん汁
ふりかけ
生卵 1個 |
朝食は、予定していたアルファ米をハイゼックスに変更。生卵かけとしました。
非常時を想定し、冷蔵庫にある野菜を使ったけんちん汁が、暖かさを与えてくれました。
食事は団欒のひと時として、大切にしました。 |
 |
 |
 |
|
 |
|
クリックしてください。 |
避難所運営ゲーム(HUG)で遊びました。
次々と読み上げられるカード(右写真)の内容によって、どの部屋に割り当てるか話し合うもので、被災者の状態が様々であることを学びました。
指導者から「平時の準備が大切」と告げられました。 |
クリックしてください。 |
|
 |
 |
前段で清水区総務防災課から区の防災体制、自主防災会による避難所の運営、自身を守るための家具固定など、阪神淡路の10倍といわれる巨大地震への対応について説明をいただきました。
続いて静岡市福祉総務課から災害時用援護者の対策について、考え方や取り組みに状況、自主防災会に対するアンケート調査の模様などについて説明をいただきました。 |
|
 |
すべての訓練を終了し、感想を話し合いました。
障がいのある人を対象とした「福祉避難所が必要」あるいは地域の絆を深めるため「市職員との交流を望む」などの意見が聞かれましたが、もっと多くの感想を知るため「小グループでの話し合いがほしかった」と、しきりに反省しています。 |
 |
|
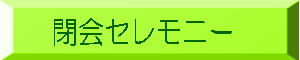 |
 |
実行委員の秋吉町自治会長から「今回の体験で皆さんと交流ができた。今後どこかで出会っても声を掛け合いたい。」とあいさつがありました。
これから交流に期待して避難所運営宿泊訓練を散会しました。 |
 |
|